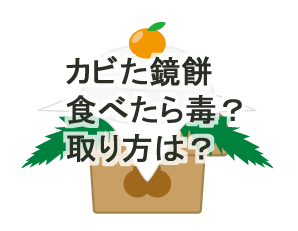
正月といえば鏡餅。
年末から鏡開きまで飾る鏡餅は、
一週間以上も室内に置いているだけあって
鏡餅がカビやすい
ですよね。
冬場はどうしても寒いのでエアコンをつけますから、
暖房が効いた部屋に置くことになりますよね。
でも風通しが良くて気温の低い場所ならカビにくいですが、
暖房をつけていて密閉度の高い場所なら
カビができる条件をがっつり満たしています。
鏡開きを迎えてみたら、鏡餅にカビが生えていた。
なんてこともよくある話です。
そんなとき、あなたならどうしますか?
食べても大丈夫か気になりますよね。
そこで今回はカビが生えてしまった鏡餅は食べられるのか?
その毒性の有無や、カビの取り方についてご紹介します。
鏡餅にカビがあっても食べられる?
鏡餅は、穀物神である「年神(歳神)」のお供え物であり、依り代です。
無病息災などを願って神様が宿られた鏡餅を頂きます。
そんな鏡餅ですが、年末から鏡開き(地域によって日付は違います)まで飾るため、
短くても一週間程度は空気に触れさせた状態で室内に置くことになります。
カビは
- 湿度(80%)
- 温度(20~30℃)
- 空気
- 栄養
が揃うと発生するので、
カビ予防をしっかり行っていなければ
飾っている間にカビが発生します。
ではそんなカビが生えてしまった鏡餅を
昔の人々はどうしていたでしょうか?
鏡餅は鏡開きまで、
カビが生えても飾るものとされています。
また、神様の宿った鏡餅を捨てるのはよろしくない、
ということで、
昔の人々はそのまま鏡餅を食べていました。
とはいってもカビが生えている部分は食べられませんので
もちろん取り除きます。
カビが出来た部分だけを取り除くので、
表面全てにカビが生えいなければ、食べていたんですね。
なので「カビが生えてしまったから食べられない!」ということはありません。
鏡餅は食べられます。
鏡餅のカビに毒性はある?
いくらカビを取り除けば鏡餅を食べられるとしても、
体に害がないか心配ですよね。
鏡餅の場合、日数的にできるカビは「緑カビ」です。
餅を始め、穀物類の初期段階にできる緑カビは食べても問題ありません。
カビだと自覚して食べると気持ち悪いですが、
少量取ったところで何ら変化はありませんので安心してください。
ですが鏡餅を数ヶ月放置してできる
黒カビは食べられません。
「黒カビ」を食べると微熱、吐き気に苦しむことになります。
鏡餅を数か月も放置する人はなかなかいないので
「間違って黒カビを食べちゃうかも!?」
なんて心配は大丈夫だと思います。
人間の胃液は鉄すら溶かせる力があります。
緑カビは弱毒性なので胃に入ると溶けてなくなってしまいます。
なので餅においてはカビの毒性よりも
噛まずに飲み食いする方が体に悪いので覚えておいてください。
とはいえ、表面のカビを取っても、
カビの菌糸は内部に深く入り込んでいます。
見えるところだけにカビがいるわけでもないので、
食べるときは焼いたりゆでたりなど加熱処理をしましょう。
餅に生えた緑カビは食べても大丈夫だとお話ししましたが、
まったくの無害というわけではないので、
ちょっとでも不快で不安を感じる方は食べない方が良いと思います。
鏡餅についたカビの取り方は?
鏡餅についたカビは、カビを含む部分を大きく取り除くことが重要です。
カビは表面から餅の内部に深く入り込みますので、表面の削り取りだけでは不十分です。
なお、鏡餅を削るときは刃物の使用は厳禁です。
刃物が切腹を連想するので使ってはいけないとされており、
カビた鏡餅には手やトンカチなどを使って取るようにします。
それ以外にも、鏡餅をお湯につけてふやかし、
タワシやスプーンなどでカビのある表面から5cmほど取り除くのもアリです。
また、アルコールをかけた後、拭いてから加熱処理も良いですね。
いずれにしても一度カビができると、
カビが再発しやすくなります。
保管する際には最初からカビができないように
予防策を施しておきましょう。
鏡餅のカビ予防については
こちらの記事でも取り上げていますのでご参考ください。

鏡餅のまとめ
鏡餅は神様の依り代で、無病息災を願っていただくものです。
カビができるとその部分は食べられなくなりますが、
全部が食べられない訳ではありません。
心情的に受け付けられないのでなければ、
カビをしっかり取り除いた上で一年の健康を願っていただきましょう。
ただし黒カビは食べても毒しかありませんので、
鏡餅を数か月放置して黒カビのついた餅は食べないように
気を付けましょう。